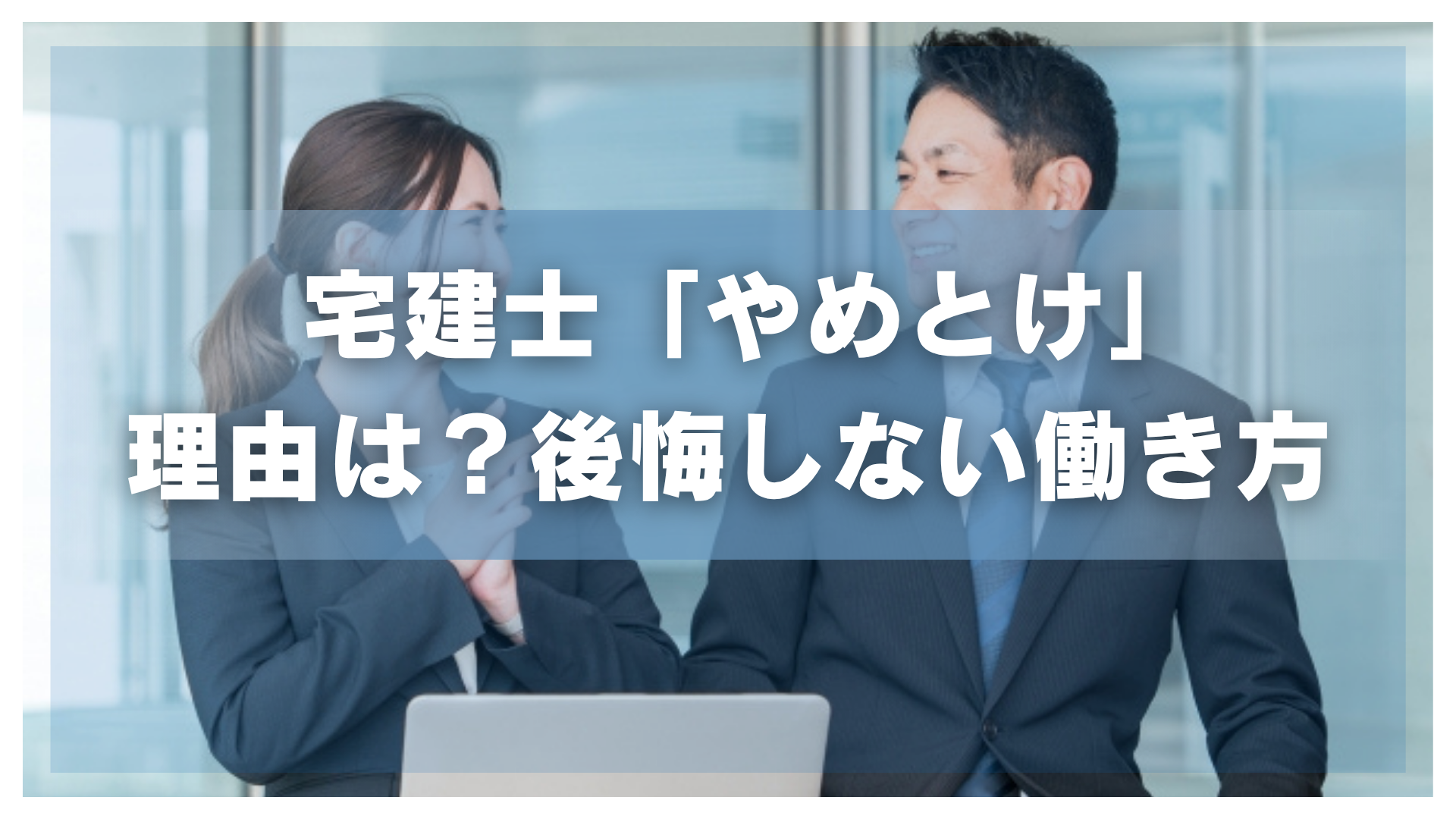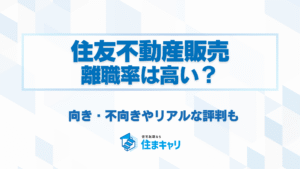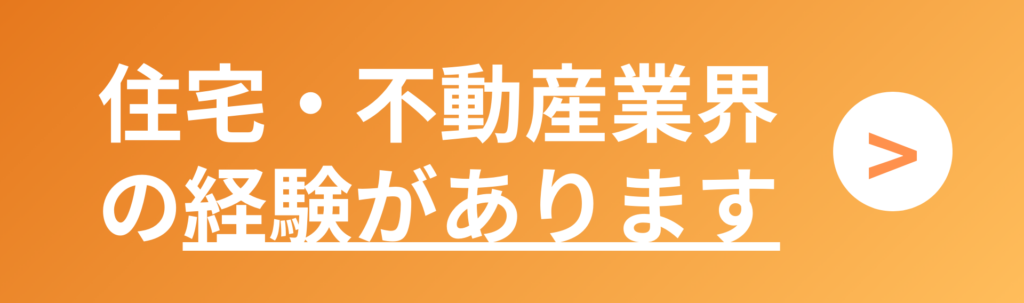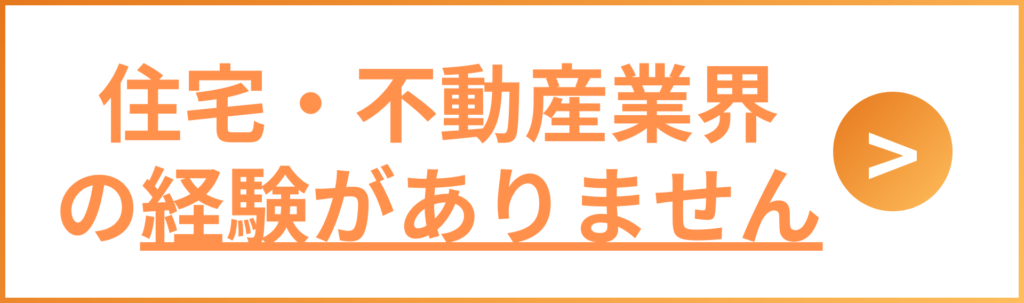宅建士は「やめとけ」「仕事がない」と言われることがありますが、それがすべての人に当てはまるわけではありません。
実際には、働き方や会社選びによって資格の価値は大きく変わります。
自分に合った職種や環境を選べば、宅建士はキャリアを広げる有力な資格になります。
この記事では、不動産業界の求人を日々見ている転職エージェントの視点から、宅建士がやめとけと言われる背景や、後悔しないための選び方を解説します。
あなたにマッチする住宅・不動産の求人をご紹介
30秒で登録完了!
住宅・不動産業界の経験はございますか?
宅建士はやめとけと言われる6つの理由
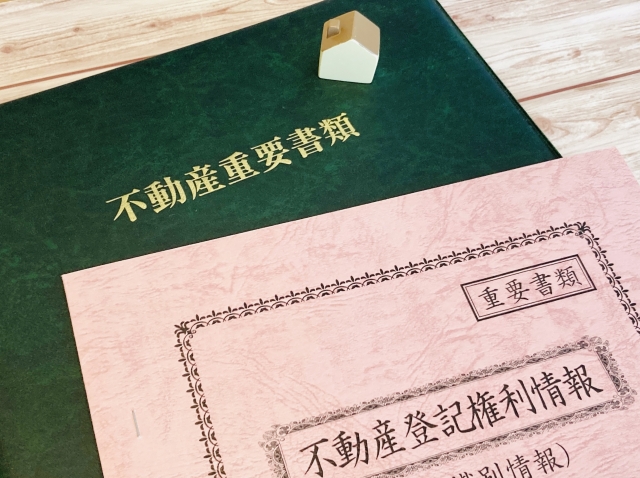
なぜ宅建士は「やめとけ」と言われてしまうのでしょうか。
その背景には、不動産業界特有のシビアな側面があります。実際に多くの人が離職理由として挙げる、より具体的でリアルな理由を解説します。
- 給与が安定しにくい場合がある
- 精神的な負担が大きい
- 仕事の負荷と時間の不規則さ
- 営業スタイルが合わないミスマッチ
- 企業や職種による環境の差が激しい
- 属人的な教育体制と人間関係
1. 給与が安定しにくい場合がある
特に売買仲介の営業職では、基本給に加えて成果給(インセンティブ)の割合が大きい会社が多く、月の売上によって収入が大きく変動します。
成果を上げれば青天井の収入も夢ではありませんが、契約がゼロの月は手取りが大幅に減ることも。
この収入の不安定さが生活への不安に直結し、「長くは続けられない」と感じる原因になります。
2. 精神的な負担が大きい
不動産は、お客様の人生を左右する高額な商品です。
そのため、一つのミスも許されないというプレッシャーが常にかかります。
さらに、物件の欠陥や騒音トラブル、家賃滞納など、顧客からの厳しいクレームや板挟みの対応に追われることも少なくありません。
こうした精神的なストレスが積み重なり、心身ともに疲弊してしまう人もいます。
3. 仕事の負荷と時間の不規則さ
営業ノルマの達成に向けたプレッシャーはもちろん、お客様の都合が最優先されるため、勤務時間は不規則になりがちです。
平日の夜遅くの商談や、土日の内見案内で休みが潰れることも日常的。
特に繁忙期はプライベートとの両立が難しくなり、ワークライフバランスを重視する人にとっては厳しい環境と感じられます。
4. 営業スタイルが合わないミスマッチ
「宅建士=営業」というイメージ通り、求人の多くは営業職です。
しかし、営業の中にも、新規の電話営業や飛び込み訪問を重視する会社もあれば、紹介や反響営業が中心の会社もあります。
泥臭い営業活動が苦手な人が前者に入社してしまうと、成果が出ずに苦しむことになります。
5. 企業や職種による環境の差が激しい
同じ不動産業界でも、扱う物件(売買/賃貸)や顧客層によって働き方は全く異なります。
さらに、同じ会社であっても支店長の方針一つで、職場の雰囲気や残業時間、営業スタイルは大きく変わります。
配属先次第で働きやすさが天国と地獄ほど変わってしまうことも、やめとけと言われる一因です。
6. 属人的な教育体制と人間関係
業界全体として人材の流動性が激しいこともあり、「見て覚えろ」というOJT中心の教育体制の会社も未だに存在します。
手厚い研修を期待して入社した未経験者が、放置されて十分に成長できないケースは少なくありません。
また、成果主義が強い職場では、同僚がライバルとなり、チームで協力する雰囲気が希薄な場合もあります。
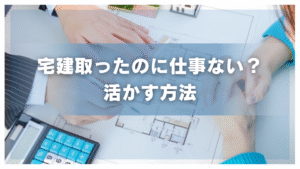
宅建士が向いている人・活かしやすい人の特徴

宅建士には向き不向きがありますが、適性に合った働き方を選べば力を発揮しやすい仕事です。
ここでは、宅建士として活躍しやすい人の特徴を紹介します。
若手・未経験でも資格を武器にしたい人
宅建士は法律で事務所への設置が必要な資格のため、若手や業界未経験の方でも評価されやすい傾向があります。
資格を持つことで「基礎知識がある」「意欲が高い」と判断され、選考で不利になりにくい点が特徴です。
最初の一歩として明確な武器を持ちたい人には向いています。
人の話を丁寧に整理し、分かりやすく説明できる人
お客様の要望は最初は漠然としていることも多く、背景にある本音や条件を丁寧に聞き出す力が求められます。
さらに、ローンや契約に関する専門用語を分かりやすく説明できる人は、お客様から信頼されやすく、長く活躍できます。
決められた手続きを正確に進められる人
不動産取引は金額が大きいため、契約内容に誤りがあると大きなトラブルにつながります。
契約書類の確認や重要事項説明など、宅建士に求められる業務には正確さが欠かせません。
ルールに沿って丁寧に進める姿勢がある人はこの仕事に向いています。
知識を積み重ねて活かしたい人
不動産に関する法律や制度は更新が多く、常に新しい情報をキャッチする姿勢が求められます。
学んだ知識を実務に活かしたい人や、継続的に知識を身につけることに楽しさを感じられる人は専門性を高めやすいです。
宅建士が選べる働き方

宅建士の資格は複数の職種で活かせます。自分に合う働き方はどれか、イメージしながらご覧ください。
- 賃貸仲介
来店客への対応が中心。多くの人と接する仕事が好きな人、スピード感を持って仕事をこなしたい若手が経験を積むのに最適です。 - 売買仲介
高額な商品を扱うため、一件の契約が大きな成果につながります。成果給(インセンティブ)の割合が高く、頑張り次第で高収入を目指したい人に向いています。 - 不動産管理
物件オーナーに代わり、入居者対応や建物の維持管理を行います。営業ノルマがなく、安定した働き方をしたい人や、コツコツと業務を進めるのが得意な人に向いています。 - ハウスメーカー(住宅営業)
自社の物件を販売します。高額な買い物だからこそ、お客様と長期的な関係を築き、深い提案をしたい人にやりがいのある仕事です。 - 宅建事務・バックオフィス
営業担当のサポート役として、契約書類の作成やデータ入力、電話応対などを担います。営業は苦手でも、専門知識を活かして人を支えたい人に適しています。
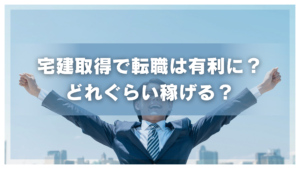
宅建士資格の現実|資格手当の相場とコストパフォーマンス

「苦労して取っても給料は上がらないからやめとけ」という声を耳がある一方、実際の金銭的な価値はどうなのでしょうか。
ここでは、資格手当の相場とコストパフォーマンスを整理します。
資格手当の相場は月1〜3万円
多くの不動産会社では、宅建士の資格保有者に対して月1〜3万円程度の資格手当が支給されています。
年間で12万〜36万円の収入アップになる計算です。資格取得にかかった学習費用を回収しやすく、毎月の固定収入を底上げできるというメリットがあります。
採用市場における資格のコストパフォーマンス
宅建士は、司法書士や弁護士のような難関資格に比べ、短期間の学習で合格を目指せる点が特徴です。
それにも関わらず、資格手当の支給や転職での優位性が得られるため、費用対効果の高い資格と言えます。
資格を持つことで求人の選択肢が増え、将来的な年収レンジを広げるための有効な投資となります。
宅建士の将来性|AI時代でも価値が残る理由

「AIの進化で仕事がなくなるからやめとけ」という声もありますが、宅建士の仕事は今後も消えることはありません。
AIが進んでも価値が残る理由を解説します。
AIでは代替できない対人折衝と最終責任
AIは契約書の作成やデータ整理を効率化できますが、次の二つは人が担う必要があります。
お客様の家族構成やライフプラン、言葉にしづらい不安を読み取って提案を行う力は、AIでは補えません。
また、不動産取引で義務付けられている「重要事項説明」は、宅建士が対面で説明し、記名押印する必要があります。
この最終責任をAIが負うことはできません。
法改正や制度変更への専門的な解釈力
不動産に関する法律や制度は社会情勢に合わせて頻繁に改正されます。
新しいルールの背景を理解し、お客様に分かりやすく伝えるためには、専門的な解釈力が欠かせません。
こうした役割は今後も人に求められ続けるため、宅建士の価値が失われることはありません。
宅建士として働く環境は会社選びで大きく変わる

同じ職種でも、どの会社で働くかによって環境は全く異なります。
資格を活かせるかどうかは、この「会社選び」が9割と言っても過言ではありません。
- 企業規模(大手・中堅・地場)で働き方が違う
大手は研修制度や福利厚生が手厚い一方、異動の可能性もあります。地場企業は転勤がなく地域に密着できますが、社長の方針が社風に強く反映される傾向があります。 - 支店長の方針で雰囲気が変わる
特に営業職は、支店長の方針一つで残業時間や営業スタイルが大きく変わります。「チームで目標を追う」支店もあれば「個人が実力で競い合う」支店もあり、雰囲気は様々です。 - 研修制度の充実度に差がある
未経験者をじっくり育てる文化のある企業もあれば、「現場で見て盗め」というスタイルの企業も未だに存在します。入社後の成長を考えると、教育体制の確認は必須です。
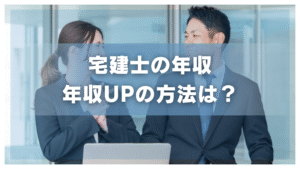
未経験・若手が後悔しないために大事なのは“職種×会社”のマッチング

「宅建士はやめとけ」という後悔の声の多くは、この「職種」と「会社」の組み合わせ、つまりマッチングの失敗から生まれています。
特に、求人票に書かれている情報だけでは、支店のリアルな雰囲気や実際の残業時間まで見抜くことは困難です。
私たち「住まキャリ」は、住宅・不動産業界の求人を2,500件以上扱い、年間3,000名以上の方からキャリア相談をいただいています。
宅建を取得したばかりの方や、これから受験を考えている未経験の方のサポート実績も豊富です。
企業の人事担当者から直接ヒアリングした「職場のリアルな情報」をもとに、あなたの希望や適性に合った職種と企業を一緒に見つけます。
一人で悩まず、まずは気軽にあなたの話を聞かせてください。
住宅・不動産業界の
無料キャリア相談、
やってます。
現場のプロに
直接質問してみませんか?
\会員登録不要・簡単30秒!/
宅建士でよくある質問(FAQ)

宅建士は独学で合格できますか?
はい、独学でも十分に合格は可能です。市販のテキストや過去問題集も充実しているため、計画的に学習を進められる方であれば合格を目指せます。
宅建を取ったら正社員になれますか?
なれる可能性は非常に高いです。不動産会社には法律で宅建士の設置義務があるため、資格保有者は常に需要があります。特に若手や未経験の方は、ポテンシャルを評価されやすく、正社員への道が拓けます。
営業が不安でも働けますか?
はい、働けます。前述した不動産管理や宅建事務のように、営業ノルマがなく、専門知識を活かして安定的に働ける職種も多くあります。
まとめ|宅建士は「やめとけ」ではなく“使い方次第”。迷う人ほど専門家に相談を

宅建士が「やめとけ」と言われるのは、一部の働き方や環境が合わなかった人の声が目立っているに過ぎません。
資格の価値は、あなたに合った職種や会社を選べるかどうかで決まります。
この記事を読んで、少しでも選択肢の多さに気づいていただけたなら幸いです。自分一人で最適な環境を見つけるのが難しいと感じたら、業界の内部情報に詳しい専門家に相談するのも有効な手段です。
後悔のないキャリアを歩むために、ぜひ一歩踏み出してみてください。
あなたの価値を最大化する、住まキャリの伴走サポートとは
転職活動がうまくいかない最大の理由は、自分一人で全てを抱え込んでしまうことです。
住宅・不動産特化型エージェント住まキャリは、下の図にあるような一連のサポートを「あなた専属の戦略パートナー」として提供します。


住まキャリを使えば、あなたの転職はこう変わります。
- 求人探しが変わる
あなたの経験(経験者)や将来性(若手)を正しく評価してくれる、Web非公開の優良求人だけをご紹介。ミスマッチを防ぎます。 - 選考準備が変わる
あなたの強みを最大限に引き出す応募書類の作成から面接対策まで、プロが徹底的に伴走。自信を持って選考に臨めます。 - 面倒な交渉がなくなる
一番言いにくくて、一番大事な「年収」や「待遇」の交渉は、すべて私たちにお任せください。あなたが納得できる条件を引き出します。
あなたの市場価値、一度プロの視点で確かめてみませんか?
今の会社で働きながらの情報収集だけでも、もちろん歓迎です。まずは無料相談で、あなたの可能性を広げる一歩を踏み出しましょう。
※情報収集だけでも歓迎。無理な勧誘は一切ありません。