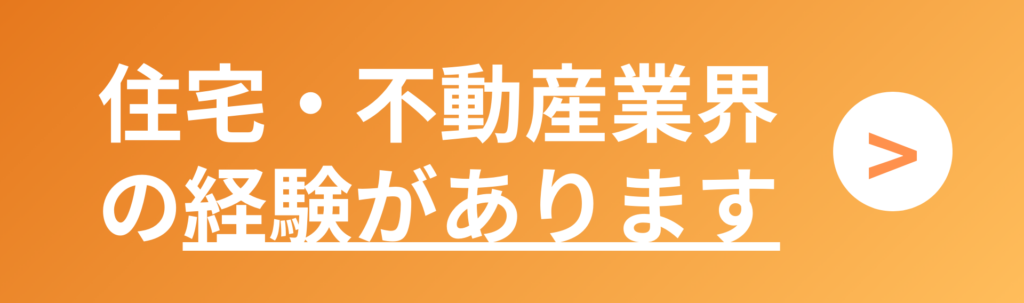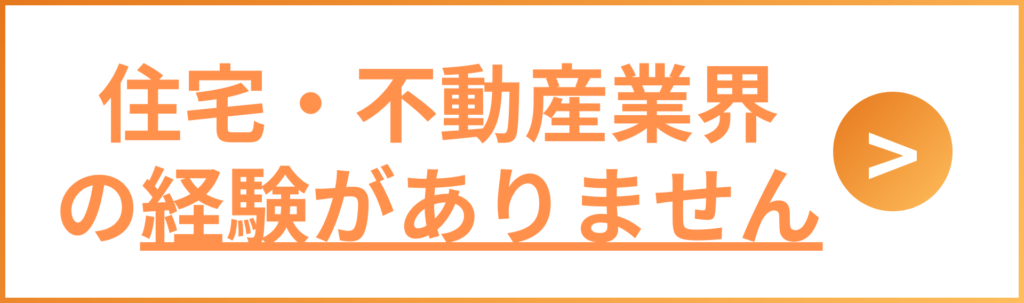国土交通省によると、全国的に空き家の増加が続く中、相続や高齢化を背景とした“管理されない空き家”が社会課題として浮上しています。
空き家の放置は、防災や景観、地域安全にも影響することから、国は定期的に「空き家所有者実態調査」を実施しています。
この調査は昭和55年から5年ごとに行われており、今回で10回目。
全国約1万3千世帯を対象に、所有経緯や管理状況、活用意向などを把握するもので、空き家対策の基礎資料として活用されます。
新たな動き
令和6年の調査では、「相続空き家」に関する新項目が設けられ、相続前の対策状況や活用意向などを詳細に把握しました。
国交省が8月29日に公表した結果によると、相続によって空き家を取得した世帯は全体の約3割を占め、そのうち2割は名義変更や登記を行っていないことが明らかになりました。
また、所有者のうち約4割が「空き家のままにしておく」と回答し、賃貸や売却を希望する割合(約2割)を上回る結果となりました。
特に「物置として必要」「解体費用をかけたくない」といった理由が多く、管理コストの高さが処分をためらう要因になっているようです。
課題

調査結果からは、依然として空き家の約半数に腐朽・破損があることも確認されています。
特に別荘や貸家以外の「その他の空き家」では、6割を超える物件で劣化が進行しており、管理不全リスクが高まっています。
一方で、所有者の約7割は「空き家まで1時間以内」に居住しており、物理的な管理は可能であるにもかかわらず、実際の維持管理が追いついていないケースが多いようです。
地域によっては人材・資金・行政支援の不足が課題となっており、国交省は調査データを自治体と共有し、地域ごとの支援策に活かす方針を示しています。
取り組み
本調査は、民間調査会社ランドブレイン株式会社に委託して実施されました。
国交省は今後、調査結果をe-Stat(政府統計ポータルサイト)を通じて公開し、自治体や研究機関、民間事業者による分析・政策立案に活用できるよう整備します。
また、前回調査(令和元年)と比較して、空き家の「利用意向」「相続前対策」「寄付・贈与意向」といった新たな視点が加わったことから、次期空き家対策法改正に向けた検討材料となる見込みです。
展望

今回の調査は、空き家問題が「管理」から「承継・利活用」へと軸足を移していることを示しています。
今後は、相続発生前の早期対策や、地域単位での活用支援スキームが求められるでしょう。
国交省は、データを活用した政策連携を進めるとともに、所有者への啓発や自治体の対策支援を強化する方針です。
空き家の発生を未然に防ぐ「予防的施策」への転換が、次の焦点となりそうです。
住まキャリの見解
『住まキャリ』編集部では、今回の調査結果を「空き家対策の転換点」とみています。
これまでの撤去・処分中心の対策から、相続前の相談体制や活用支援へのシフトが進むことで、地域再生の新たな機会が生まれると考えます。
特に、空き家を「地域資産」として利活用するためには、所有者と行政・民間が協働する仕組みづくりが不可欠です。
今後も『住まキャリ』では、空き家対策の動向と地域まちづくりの関係性を継続的に追っていきます。