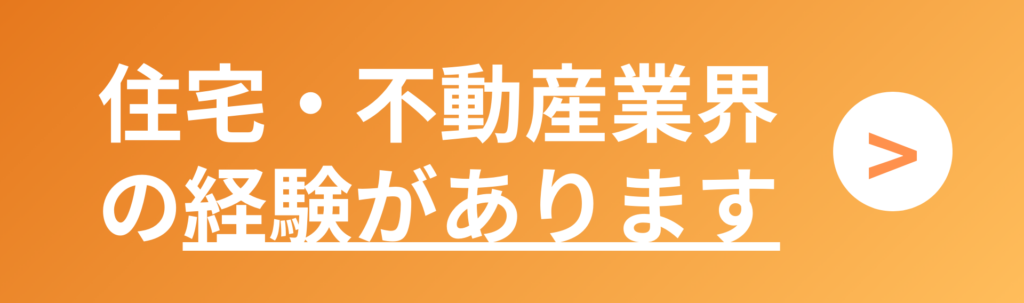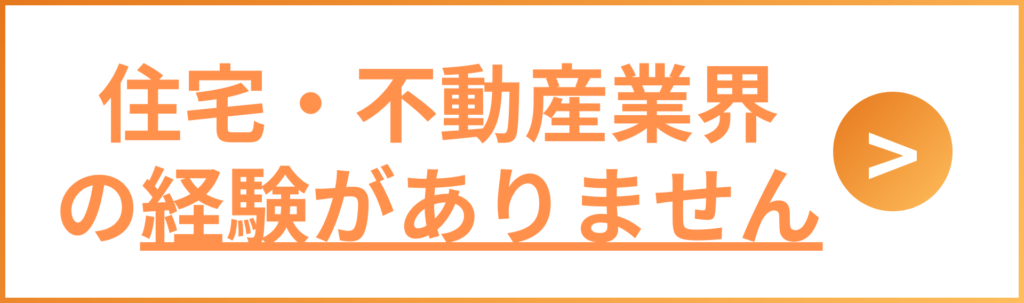一級建築施工管理技士はなぜ「すごい」と言われるのでしょうか。
受験には実務経験が必要で、合格率も高くはなく、取得すれば法律で必置とされる責任者「監理技術者」として現場を任されることができます。
本記事では、一級建築施工管理技士が「すごい」と評価される理由、年収や待遇の実情、試験の難易度、さらに転職市場での評価までを実務目線で解説します。
資格取得を目指す若手施工管理職から、すでに資格を持つ経験者まで、キャリアを考える上で役立つ情報をまとめました。
一級建築施工管理技士が「すごい」といわれる理由

一級建築施工管理技士は、建設業界で「持っていると一目置かれる資格」として知られています。なぜそこまで評価が高いのか、その理由を整理すると大きく3つに分けられます。
- 難関資格で専門性を証明できる
- 大規模工事を任される
- キャリアや昇進に直結する
難関資格で専門性を証明できる
一級建築施工管理技士は、実務経験が受験資格として必須であり、第一次検定(学科)と第二次検定(実地)の両方に合格しなければなりません。
しかし、学科と実地を同じ年度で突破できる人は全体の15%程度にとどまります。
最終的に合格に到達できるのは受験者の一部に限られるため、専門性を証明できる難関資格と評価されています。
大規模工事を任される
一級を取得すると、法律上「監理技術者」として配置することが可能になります。監理技術者とは、元請企業が下請に工事を出す場合に必ず専任配置が義務付けられている重要な役割です。
大規模な公共工事や都市開発の現場では監理技術者なしに現場を動かせないため、資格を持っている人は現場の中核を担う存在となります。
2級や無資格では担当できない領域を任されることが、一級の「すごさ」を裏付けています。
キャリアや昇進に直結する
資格を持つことで現場責任者としての評価が高まり、昇進や昇給にも直結します。
企業によっては資格手当が月額3万円前後支給されることもあり、年収にして30万〜60万円程度の差がつくケースも珍しくありません。
さらに、役職やプロジェクトの規模に応じて年収が大きく伸びる可能性があります。
 CA小竹
CA小竹若手にとっては将来のキャリア形成の武器になり、経験豊富な施工管理職にとっては管理職や部門長への道を開く資格といえるでしょう。
一級建築施工管理技士の年収はどれくらいすごい?待遇の実情


平均年収は業界全体でも高水準
厚生労働省「職業情報提供サイト(job tag)」によると、建築施工管理技術者の平均年収は約632.8万円とされています。
また、同省が公表した「令和6年 賃金構造基本統計調査」によれば、建設業全体の平均年収は約581万円です。
これを踏まえると、施工管理技術者の収入水準は業界全体の平均を大きく上回っていることがわかります。
特に一級建築施工管理技士を保有している場合は、現場の責任者や監理技術者としての役割を担うことができるため、さらに高い給与が期待できます。
出典:厚生労働省job tag 令和6年 賃金構造基本統計調査


年代や会社規模によって大きく変わる
年収は年齢に加えて、勤務する会社の規模や業態によっても大きく変動します。
大手ハウスメーカーやゼネコンに勤める場合、20代でも500万円前後に届きやすく、30代後半から40代には700万円を超えるケースもあります。
一方で、地域密着型の工務店や中小規模の建設会社では、20代は400万円台にとどまることもあり、昇給も緩やかな傾向があります。
厚生労働省の統計でも、下位25%が約385万円、上位25%が約841万円と幅が大きく、所属する会社の規模や担当する工事の種類が待遇に直結していることが読み取れます。
資格手当や昇給事例でさらに上がる
一級建築施工管理技士の資格を持つことで、基本給に加えて資格手当が支給されるのも大きな特徴です。
求人票などから確認できる相場では、月額30,000円前後(幅として10,000円~50,000円程度)が一般的です。年間に換算すると30万~60万円程度が上乗せされる計算になり、昇給や賞与の評価にも直結します。
また、同じ厚労省の職業データでも、経験年数や役職に応じて収入が伸びる傾向が明確に示されており、資格を持つことで長期的に安定した高収入を築きやすい職種といえるでしょう。
一級建築施工管理技士の難易度はすごい?


一級建築施工管理技士は、建設業界における現場監督の最高峰資格です。
ここでは試験の特徴、合格率の推移から難易度を見ていきます。
学科・実地試験の特徴
- 72問中60問を解答(必須/選択構成)
- 午前2.5時間+午後2時間の長時間形式
- 合格には総得点60%以上かつ応用能力も60%以上
- 建築学・施工管理法・法規・応用能力と範囲が広い
- 記述式6問すべて必須、施工経験記述は例年出題される
- 多岐にわたる施工・管理・法規などが問われる
- 合格率は40〜50%前後、難易度が高いと感じる受験者も多い
- 学科合格の有効期間(2年)がある点も重要(要確認)
知識の広さだけでなく、現場での経験を整理して表現できる力も求められるのが特徴です。
合格率の推移
直近の合格率は以下の通りです。
| 年度 | 第一次検定合格率 | 第二次検定合格率 | 最終合格率(目安) |
|---|---|---|---|
| 2020年 | 51.1% | 40.7% | 約20% |
| 2020年 | 36.0% | 52.4% | 約19% |
| 2020年 | 46.8% | 45.2% | 約21% |
| 2020年 | 41.6% | 45.5% | 約19% |
| 2020年 | 36.2% | 40.8% | 約15% |
学科試験は例年40〜50%程度が合格し、実地試験も40〜50%前後と、一見「半分は通る」ように見えます。
しかし両方を同じ年に突破できるのは全体の15〜20%程度に限られ、数字の印象よりも難関であることがわかります。



受験資格として数年以上の実務経験が必要で、現場仕事と並行して勉強時間を確保しなければならない人が多いため、合格率以上に難関といえます。
一級建築施工管理技士になるためのポイント


1級建築施工管理技士は最終合格率が15〜20%前後にとどまる難関資格ですが、正しい準備をすれば突破は十分可能です。
合格を目指すには、受験資格の確認から学習計画、現場経験の整理、学習環境の工夫までを意識することが大切です。
受験資格を確認する
第一次検定(学科試験)は、2024年度から学歴や実務経験の制限が撤廃され、満19歳以上であれば誰でも受験可能です。
ただし、第二次検定(実地試験)を受けるには、学科試験に合格していることに加えて、施工管理業務に関する実務経験が必要です。
ここでいう実務経験とは、建築工事の施工計画、工程管理、品質管理、安全管理など、現場での管理業務に従事した期間を指します。
必要な年数は学歴や学科によって異なり、たとえば
- 大学・高専(指定学科)卒:3年以上
- 短大・高専(指定学科)卒:5年以上
- 高校(指定学科)卒:10年以上
- 学歴不問:通算15年以上
といった目安があります(令和10年度までは旧制度による受験資格の経過措置も適用)。



学科合格は2年間有効なので、その間に必要な実務経験を満たしているか確認し、計画的に実地試験の準備を進めることが重要です。
学習スケジュールを立てる
出題範囲は施工管理法、建築学、法規、施工一般など幅広く、短期的な勉強だけでは対応できません。
半年〜1年を目安に、平日は1〜2時間、休日はまとまった時間を確保するなど、計画的に学習を進めることが重要です。特に暗記分野は早めに取り組んでおくと直前期に余裕が生まれます。
現場経験を整理する
実地試験では、自身の施工経験を題材に記述する問題が出題されます。
工事規模や工期、安全管理の工夫、担当した役割などを日報やメモにまとめておくと、答案作成に直結します。
日々の経験を体系的に整理しておくことが、合格の大きな鍵になります。
通信講座や予備校を利用する
独学で合格する人もいますが、効率を考えると通信講座や予備校の活用も有効です。
添削指導や模試を受けることで、経験記述の書き方や出題傾向に合わせた答案作成が可能になります。特に文章表現に不安がある場合は、第三者のフィードバックを受けることで弱点を補強しやすくなります。
一級建築施工管理技士の転職市場の評価はすごい?


ここからは、一級建築施工管理技士の転職市場の評価をまとめました。以下のポイントを確認しておきましょう。
- 監理技術者・主任技術者になれる
- ゼネコン・大手ハウスメーカーなどで活躍できる
- そもそも転職市場での需要が高い
監理技術者・主任技術者になれる
1級を保有していると、建設業法上の必置ポジションである監理技術者や主任技術者を務められます。
大規模案件や元請工事では配置が義務づけられるため、企業は有資格者を確保するほど受注の選択肢が広がります。
結果として、採用選考での評価やオファー年収で優位に働きやすく、現場のキーパーソンとして配属される可能性も高まります。
なお、設備主体の案件では管工事・電気工事の各1級が求められる場合もあるため、担当領域との適合は事前に確認しておくと安心です。
ゼネコン・大手ハウスメーカーなどで活躍できる
1級を取得していれば、働く場所や活躍できるフィールドを広げます。
ゼネコンでは共同住宅や商業施設、オフィス、病院、学校などの新築・改修で工事主任や所長候補として期待され、ハウスメーカーやリフォーム会社では戸建や大型リノベで品質・工程・安全を統括する役割を担えます。
元請だけでなく専門工事会社や内装・S造・RC造の各領域でも評価されるため、キャリアの選択肢が増える点が強みです。
もっとも、各社の得意構造や工種によって求める実績は異なるため、直近3〜5年の担当用途・規模・役割を整理して示せるようにしておくと効果的です。
そもそも転職市場での需要が高い
受注の平準化や老朽更新、改修ニーズの増加、加えて人材の世代交代により、施工管理職の採用需要は高止まりが続いています。
法定の有資格者配置が必要な現場が多いこともあり、1級保有者は求人の選択肢が広く、複数社から比較検討できる状況が生まれやすいのが現状です。



とはいえ、地域や案件特性によって年収水準・働き方は差が出るため、希望条件に合う市場を見極めることが大切です。
一級建築施工管理技士の転職を成功させる方法


一級建築施工管理技士は資格そのものに強い価値がありますが、転職を確実に成功するためには、いくつか事前に知っておくべきことがあります。
- 年収やキャリアの希望条件を明確にする
- 応募先企業の情報を徹底的にリサーチする
- 転職エージェントを活用して選択肢を広げる
年収やキャリアの希望条件を明確にする
まずは優先順位を整理することが重要です。
年収、担当したい案件の種類(マンション、商業施設、戸建など)、新築か改修か、所長を目指すのか専門分野に特化するのか、転勤や残業の可否などを具体的に決めておくと、応募先の選定や面接での自己PRに一貫性が出ます。
応募先企業の情報を徹底的にリサーチする
事業領域や案件規模、地域密着か広域展開か、人員体制や働き方の特徴などを確認し、応募先と自分の経験と接点を見つけておきましょう。
例えば「RC造マンションで所長を務めた経験があり、同社の集合住宅案件でも即戦力になれる」と具体的に語れるよう準備することが、評価を高めるポイントになります。
転職エージェントを活用して選択肢を広げる
建設・不動産に強い転職エージェントを使うと、非公開求人の紹介や条件交渉、職務経歴書のブラッシュアップなどで効率よく転職活動を進められます。
自分では言語化しにくい強みを客観的に整理してもらえるのも大きなメリットで、希望に合った企業と出会いやすくなります。
あなたの価値を最大化する、住まキャリの伴走サポートとは
転職活動がうまくいかない最大の理由は、自分一人で全てを抱え込んでしまうことです。
住宅・不動産特化型エージェント住まキャリは、下の図にあるような一連のサポートを「あなた専属の戦略パートナー」として提供します。




住まキャリを使えば、あなたの転職はこう変わります。
- 求人探しが変わる
あなたの経験(経験者)や将来性(若手)を正しく評価してくれる、Web非公開の優良求人だけをご紹介。ミスマッチを防ぎます。 - 選考準備が変わる
あなたの強みを最大限に引き出す応募書類の作成から面接対策まで、プロが徹底的に伴走。自信を持って選考に臨めます。 - 面倒な交渉がなくなる
一番言いにくくて、一番大事な「年収」や「待遇」の交渉は、すべて私たちにお任せください。あなたが納得できる条件を引き出します。
あなたの市場価値、一度プロの視点で確かめてみませんか?
今の会社で働きながらの情報収集だけでも、もちろん歓迎です。まずは無料相談で、あなたの可能性を広げる一歩を踏み出しましょう。
※情報収集だけでも歓迎。無理な勧誘は一切ありません。
一級建築施工管理技士はすごい資格


一級建築施工管理技士は、受験資格に実務経験が必要で、合格率も最終的に15〜20%前後にとどまる難関資格です。
その分、取得すれば現場での信頼性はもちろん、転職市場でも高い評価を得られる大きな武器になります。
資格を活かしてキャリアを広げるためには、学習や経験の積み重ねに加えて、自分の希望条件を整理し、働き方に合う職場を見極めることが大切です。
転職を意識している人はもちろん、情報収集の段階にある人も、業界に詳しい相談先を持っておくことで安心して次の一歩を踏み出せるでしょう。
あなたにマッチする住宅・不動産の求人をご紹介
30秒で登録完了!
住宅・不動産業界の経験はございますか?