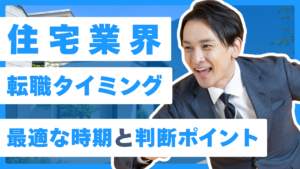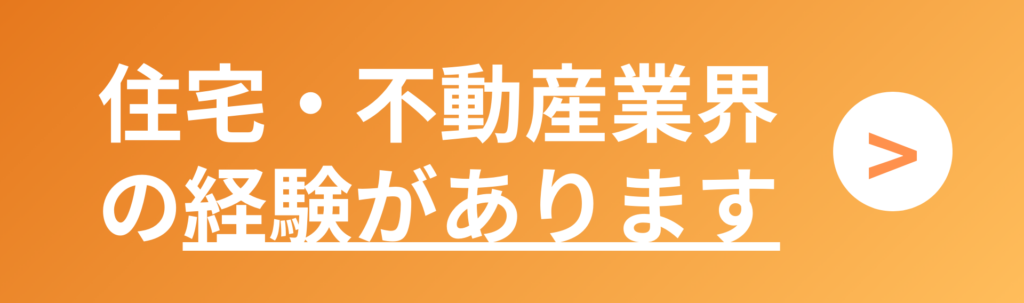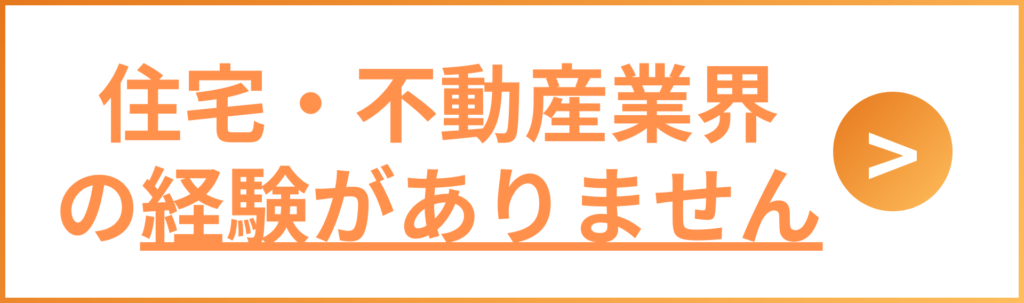「施工管理は離職率が高い」という話を耳にして、転職を迷っていませんか?
確かに建設業界全体の離職率は他業界と比べて高い傾向にありますが、実際の数値や理由を正しく理解することで、あなたに合った転職判断ができるはずです。
この記事では、最新の統計データをもとに施工管理の離職率の実態を詳しく解説し、転職成功のためのポイントをお伝えします。施工管理へのチャレンジを検討している方は、ぜひ参考にしてください。
\ あなたに合った不動産営業の求人をご紹介します! /
住宅・不動産エージェント住まキャリでは、業界の生の情報から、あなたに合った優良企業のご紹介まで、現役のキャリアアドバイザーが完全無料でサポートします。
- 未経験歓迎の求人多数
- 高収入・高インセンティブの求人もご用意
- 登録はたった30秒!
施工管理の離職率は28.6%【最新統計データで解説】
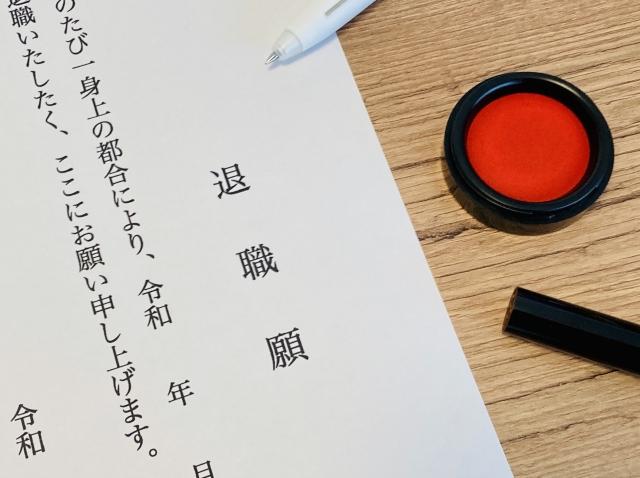
厚生労働省の「雇用動向調査」によると、建設業の離職率は28.6%となっており、全産業平均の14.2%を大きく上回っています。施工管理職も建設業に含まれるため、この数値が参考になります。
ただし、施工管理の中でも不動産・住宅系と建設現場系では状況が異なり、また企業規模や働き方によっても大きく差が出ているのが現状です。
重要なのは、数値だけで判断せず、なぜ離職率が高いのか、どのような企業なら長く働けるのかを理解することです。
出典:厚生労働省
他業界との離職率比較表
建設業の離職率28.6%と比較すると、製造業は9.8%、金融・保険業は9.4%、情報通信業は11.8%となっており、建設業の離職率の高さが際立っています。
一方で、宿泊・飲食サービス業は30.3%、生活関連サービス業は24.9%となっており、施工管理を含む建設業だけが特別に高いわけではありません。
IT業界でも新興企業では20%を超える場合も多く、業界の性質や企業の成熟度によって離職率は大きく変動します。
年代別・経験年数別の離職率
施工管理の離職率は年代によっても大きく異なります。
20代前半の離職率は約40%と高く、特に入社後3年以内の離職が多いのが特徴です。これは業務の厳しさを実感する時期と重なります。
一方、30代以降は15%程度まで下がり、40代では10%を下回ります。経験年数別では、1年未満が最も高く35%、3年以上経験すると10%以下に安定します。
つまり、最初の3年間を乗り越えることができれば、長期的なキャリアを築ける可能性が高まります。未経験からの転職者は、この期間の乗り越え方が成功の鍵となります。
不動産・住宅系と建設系での離職率の違い
不動産・住宅系の施工管理は建設現場系と比べて離職率が低い傾向にあります。不動産系では22%程度、建設現場系では32%程度と約10ポイントの差があります。
これは働き方の違いが大きく影響しており、不動産系は比較的規則的な勤務時間で働けることが多く、現場での肉体的負担も少ないためです。
また、不動産系は顧客との打ち合わせやプロジェクト管理が中心となるため、コミュニケーション能力を活かしやすい環境です。
ただし、不動産市況の影響を受けやすいという特徴もあるため、転職時は企業の安定性も併せて確認することが重要です。
施工管理を辞める人の理由トップ4

施工管理を離職する人の主な理由は、①長時間労働、②人間関係のストレス、③給与への不満、④キャリアアップの限界の4つに集約されます。
これらの理由は企業選びや働き方によって大きく改善できる場合が多いため、転職前にしっかりと対策を考えておくことが重要です。
また、これらの課題を解決している企業も存在するため、すべての施工管理職が同じ問題を抱えているわけではないことも理解しておきましょう。
長時間労働・休日出勤の実態
施工管理の長時間労働は業界全体の課題となっています。
月平均残業時間は60時間を超える企業も多く、工期の関係で休日出勤も頻繁に発生します。特に建設現場系では、現場の進捗に合わせて早朝や夜間の対応が必要になることもあります。
 CA小竹
CA小竹しかし、近年は働き方改革の影響で改善に取り組む企業が増えており、残業時間の上限設定や有給取得の推進を行う会社も出てきています。
不動産系の施工管理では、比較的規則的な勤務時間で働ける企業も多く、転職時の企業選びで労働環境は大きく変わる可能性があります。
人間関係・現場でのストレス
施工管理は多くの関係者との調整が必要な職種で、職人さん、設計者、発注者など様々な立場の人とのコミュニケーションが求められます。
特に工期の遅れや品質問題が発生した際は、板挟みになってストレスを感じることが多くあります。現場での厳しい環境や、経験豊富な職人さんとの年齢差によるコミュニケーションの難しさも離職理由の一つです。



ただし、これらは経験を積むことで徐々に改善される場合が多く、また企業によってはコミュニケーション研修やサポート体制を整えているところもあります。
人間関係のストレスは個人の適性によるところも大きいため、事前の見極めが重要です。
給与面での不満
施工管理の給与水準は企業規模や経験年数によって大きく異なります。
未経験者の初年度年収は300万円台前半からスタートすることが多く、他の専門職と比べて低く感じる場合があります。また、長時間労働に対して時給換算すると割に合わないと感じる人も少なくありません。



ただし、これらは経験を積むことで徐々に改善される場合が多く、また企業によってはコミュニケーション研修やサポート体制を整えているところもあります。
しかし、経験を積み、資格を取得することで年収500万円〜800万円まで上昇する可能性があり、将来的な昇給幅は比較的大きい職種です。
不動産系では成果に応じたインセンティブがある企業も多く、実力次第で高収入を得られる場合もあります。転職時は初年度の給与だけでなく、昇給の仕組みも確認することが重要です。
キャリアアップの限界
一部の企業では施工管理からの昇進ルートが限定的で、現場の管理職止まりというケースがあります。
特に中小企業では管理職のポジションが少なく、キャリアアップの機会が限られることがあります。また、技術系の専門職としての成長は見込めるものの、経営層への道筋が不明確な企業も存在します。



しかし、大手不動産会社や総合建設会社では、施工管理から事業部長や役員まで昇進できるキャリアパスが整備されている場合も多く、企業選びによってキャリアの可能性は大きく変わります。
転職時は将来のキャリアビジョンを明確にし、それが実現可能な企業を選ぶことが重要です。
「施工管理はやめとけ」は本当?向き不向きを見極める


「施工管理はやめとけ」という声をよく聞きますが、これは万人に当てはまるわけではありません。施工管理には確かに厳しい面もありますが、同時に大きなやりがいや成長機会も存在します。
ここでは、施工管理に向いている人の特徴や成功パターンを具体的に解説し、あなた自身の適性を判断する材料を提供します。
施工管理に向いている人の特徴
施工管理に向いているのは、責任感が強くリーダーシップを発揮できる人です。
複数の作業班を統括し、工期とコストを管理する能力が求められるため、計画性と実行力を併せ持つ人が成功しやすい傾向にあります。
また、様々な職種の人とコミュニケーションを取る必要があるため、人当たりが良く調整能力に長けた人も適性があります。
物事を論理的に考えて問題解決できる人、そして何より建物が完成した時の達成感を重視できる人は、施工管理の仕事に大きなやりがいを感じることができるでしょう。
ストレス耐性があり、さまざまな状況に臨機応変に対応できる人も求められるでしょう。


未経験から始めて成功する人のパターン
未経験から施工管理で成功する人には共通するパターンがあります。
最初の3年間を学習期間と割り切り、積極的に知識とスキルを吸収する姿勢を持つことです。
また、現場での実践を通じて経験を積みながら、2級建築施工管理技士などの基本資格を早期に取得すれば、その後のキャリアアップもスムーズです。
あなたにマッチする住宅・不動産の求人をご紹介
30秒で登録完了!
住宅・不動産業界の経験はございますか?
離職率が低い施工管理会社の見分け方


施工管理への転職を成功させるためには、離職率が低く働きやすい企業を見分けることが重要です。同じ施工管理でも、企業によって労働環境や待遇は大きく異なります。
ここからは、求人票の読み方から面接での質問方法まで、具体的な見分け方を解説します。特に不動産・住宅業界は企業による差が大きいため、しっかりとした企業研究が転職成功の鍵となります。
求人票でチェックすべきポイント
求人票で確認できること
- 平均残業時間(目安)
- 年間休日数や週休制度
- 資格手当や取得支援の有無(制度の有無だけは分かる)
求人票だけでは分かりにくいこと
- 1人あたりの担当現場数と移動距離
- 休日出勤の頻度と振替休日の取りやすさ
- 研修内容の具体性(OJTの質、マニュアル化されているか)
- 資格手当が実際の給与にどの程度反映されるか
- 離職理由や中途入社者の定着率
求人票はあくまで最低限の目安です。
数字の根拠や実際の働き方は面接で質問するのはもちろん、自分だけで不安な場合は転職エージェントを通じて情報を補うのも一つの方法です。



疑問を残さず、納得できる職場を選びましょう。
面接で必ず聞くべき質問リスト
面接では遠慮せずに、以下のような施工管理ならではのポイントを質問すると、入社後のギャップを減らせます。
- 1日の業務スケジュール(現場移動の頻度や直行直帰の可否など)
- 繁忙期の労働時間や残業時間の目安(竣工前などピーク時の実態)
- 夜間工事や休日出勤の発生頻度と振替休日の取りやすさ
- 協力業者や職人との関係性、トラブル時のフォロー体制
- サポート体制(未経験者へのOJT、先輩同行の期間など)
- 昇進・昇格の基準(現場経験年数や資格取得との連動性)
- 退職理由で多いもの(人間関係か労働時間かなど)
- IT化・遠隔管理などの導入有無
これらを具体的に聞くことで、施工管理という仕事の現実を把握しやすくなります。
回答が曖昧な場合は、無理なく続けられる環境か慎重に判断しましょう。
住宅・不動産業界の施工管理で働きやすい会社の特徴
大手であれば、分業体制が整っている、残業代が全額支給される、研修制度が充実しているなどの働きやすさは当たり前のように備わっている場合が多いです。
一方で中堅以下の会社でも、以下のポイントができていれば無理なく続けやすい環境と言えます。
- 担当現場数が多すぎない
1人が抱える棟数が適正で、現場ごとの役割分担やサポート体制がある - 突発対応を現場任せにしない仕組みがある
施主対応のフォローやスケジュール調整を上司が手伝ってくれる - 現場ルールが属人化していない
マニュアルやチェックリストがあり、誰が担当しても工程が回る - 残業代がしっかり支給される
残業が発生してもサービス残業が黙認されない。振替休日も取りやすい - 人が人を紹介して入社する会社
規模は大きくなくても、紹介で人が集まる会社は内部満足度が低くない傾向がある



中堅以下では“制度があっても現場で機能しているか”がポイントです。
「企業の価値観は?」「どんな特徴があるの?」と、調べてもわからないことが出てくることもありますよね。
そんなときは、住宅転職エージェント住まキャリにご相談ください。
転職をお考えの方を対象に、応募先選びをプロが丁寧にサポートします。
施工管理への転職で失敗しないための準備と進め方


施工管理職へ転職を成功させるには、「情報を集める」「資格を取る」「書類と面接を準備する」「信頼できるサポートを得る」
この4つを順を追って進めることが大切です。
1. まずは業界情報を集める
求人票だけで判断せず、残業時間や現場数、分業体制などを調べておきましょう。
施工管理は会社で働き方が大きく違うので、口コミサイトや知人の話も参考に。不明点は面接で確認する前提でメモしておきます。
2. 必要な資格を計画的に取得する
施工管理職への転職では、「2級建築施工管理技士」が特に評価されやすい資格です。
2021年(令和3年)の制度改正で、実務経験がなくても学科試験だけ先に受験できるようになり、若手が早い段階で知識を身につけやすくなりました。
未経験の方は学科だけでも合格しておくと「意欲がある」と評価され、転職が有利になります。学科合格は5年間有効なので、入社後に現場経験を積んで実地試験に進めます。
経験者は2級をフルで取っておくか、1級取得を目指すと年収アップに直結しやすいです。
不動産系では「宅地建物取引士(宅建)」も持っていると施主対応やキャリアの幅が広がります。
資格勉強は働きながらだと負担が大きいため、転職活動の半年前くらいから準備を始めるのがおすすめです。


3. 応募書類と面接対策を整える
施工管理は現場をまとめる立場だからこそ、段取り力・調整力・コミュニケーション力 が特に重視されます。
職務経歴書では、「スケジュール管理をした経験」「複数人の作業を調整した経験」「取引先やお客様対応でトラブルを防いだエピソード」など、現場で活かせる具体的な行動例 を入れましょう。
未経験の方は「施工管理を選んだ理由」「資格取得の意欲」「体力面の自己管理ができる」「人とのやりとりが苦にならない」など、向いている特性を自分の言葉で説明できるように準備しておくことが大切です。
面接では、残業時間や担当現場数、休日出勤の頻度など求人票だけでは分からないリアルな働き方も必ず質問して確認しておきましょう。
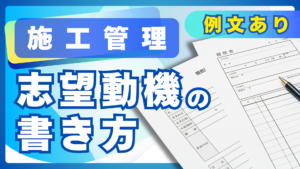
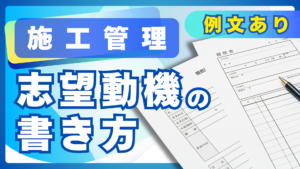
4. 専門エージェントを活用する
業界特有の情報は一人では集めきれません。
不動産・住宅業界専門の転職エージェントを活用することで、求人票だけでは分からない現場の実態を知ることができます。
また、書類添削や面接対策、条件交渉のサポートを受けられるのもメリットです。
複数のエージェントに登録し、初回面談で信頼できる担当者を見極めることも失敗しない進め方の一つです。
面接対策はエージェントで対応してくれる場合もあるため、担当のキャリアアドバイザーに聞いてみましょう。
施工管理の離職率は会社ごとに異なる 入社後ミスマッチしない対策を


文章の冒頭で「28.6%の離職率」に驚いたかもしれませんが、重要なのは平均に振り回されずに企業ごとの実態をきちんと見極めることです。
- 不動産開発系や住宅業界の施工管理は、現場への負荷が相対的に少なく働きやすいケースも多い
- 転職成功のポイントは、求人票では見えない働き方の中身を、面接やエージェントから聞き出すこと
特に若手で3年目までは厳しさがありますが、支援体制が整っている会社を選べば、安定したキャリア構築が可能です。
「離職率が高いから不安」と感じている方こそ、情報収集と準備を進めて、あなたに合う働きやすい環境を選んでください。
住宅・不動産エージェント住まキャリでは、業界の生の情報から、あなたに合った優良企業のご紹介まで、現役のキャリアアドバイザーが完全無料でサポートします。
- 未経験歓迎の求人多数
- 高収入・高インセンティブの求人もご用意
- 登録はたった30秒!