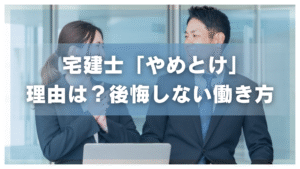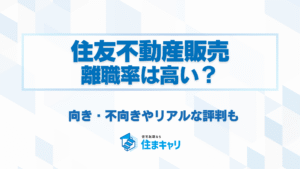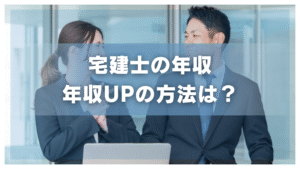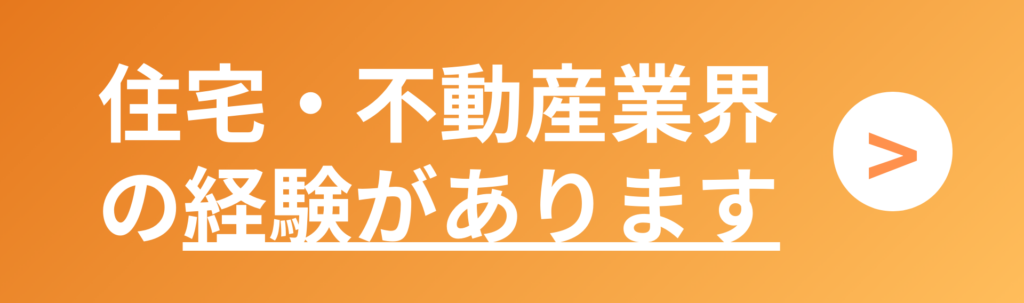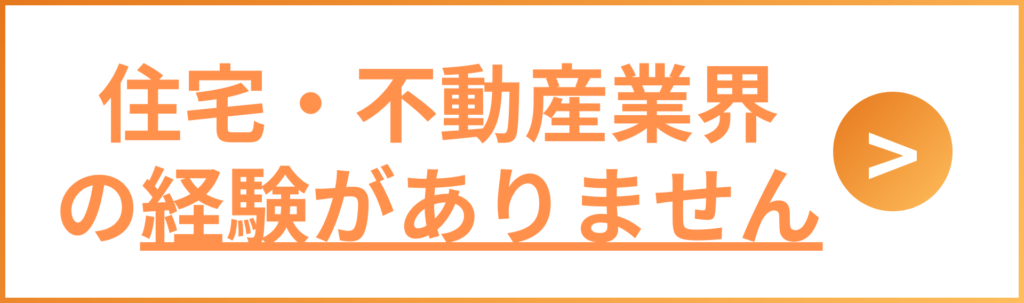「宅建を取れば、転職がうまくいくと思っていたのに……」と感じていませんか?
実は、宅建資格を持っているにもかかわらず、「思ったより仕事がない」「書類すら通らない」と悩んでいる人は少なくありません。
努力して取得したはずの資格が活かせない。その原因は、宅建資格そのものではなく、活かし方にあります。
この記事では、宅建を取ったのに仕事がないと感じる理由と、転職成功につなげるための活用法をわかりやすく解説します。
「宅建は本当にオワコンなのか?」「どうすればキャリアに結びつくのか」後悔しないようぜひ最後までご覧ください。
「宅建を取っても仕事がない」と言われる5つの理由

宅建を取っても「仕事がない」と言われる背景には、資格の性質や不動産業界の採用事情が関係しています。
ここでは、理由を5つの視点から整理して解説します。
- 宅建資格だけでは即戦力と見なされない
- 宅建資格の保有者が多く差別化が難しい
- 宅建必須の求人は意外と少ない
- 不動産業界以外では使える場面が限られる
- 営業力など「実力重視」の企業が多い
①宅建資格だけでは即戦力と見なされない
宅建は不動産業界で評価される資格のひとつですが、持っているだけで即戦力と判断されることは少なく、あくまで「プラス評価」にとどまることが多いのが実情です。
特に営業職では「資格の有無」より「契約を取れるかどうか」「自分で考えて動けるか」といった実務能力が重視されるため、未経験で資格だけ保有している状態では、採用の決め手にならないケースも少なくありません。
「宅建を取ったから転職できるはず」と思い込んでしまうと、ギャップに悩むことにもなりかねません。
②宅建資格の保有者が多く差別化が難しい
宅建は人気資格のひとつで、毎年20万人以上が受験しています。たとえば令和6年度(2024年)の試験では、受験者数は約24万人、合格率は18.6%でした。
一見すると難関資格に見えますが、実は多くの人が取得を目指しており、転職市場では「宅建を持っている人」はそれほど珍しくありません。
そのため、資格だけで他の応募者と差をつけるのは難しく、「宅建を取ったのに選ばれない」と感じてしまう原因にもなっています。
出典:不動産適正取引推進機構
③宅建必須の求人は意外と少ない
不動産業界の求人を見てみると、「宅建必須」としている企業よりも、「歓迎」や「あれば尚可」とする企業のほうが多く見られます。
中でも不動産営業の求人では「運転免許必須」「営業経験者歓迎」といった条件のほうが優先されることもあり、宅建を持っていても応募の決め手にならない場合があります。
その結果、「せっかく資格を取ったのに仕事が見つからない」と感じてしまう人が一定数いるのです。
④不動産業界以外では使える場面が限られる
宅建は不動産の専門資格であり、不動産業・住宅業においては高く評価されますが、それ以外の業界では活用の幅が限られてしまう面があります。
たとえば銀行や保険会社、建設業、法律事務所などで不動産知識が求められる場面もありますが、必須とされることは少なく、むしろ宅建よりも他の資格や経験が優先されるケースが多いです。
そのため「不動産以外の業界で働きたいけど、宅建しかない」という人は、活用方法が見えにくくなり、「仕事がない」と感じてしまう可能性があります。
⑤営業力など「実力重視」の企業が多い
とくに営業職では、「どれだけ契約を取れるか」「顧客との信頼関係を築けるか」が成果に直結するため、資格の有無よりも実力で評価される傾向があります。
実際に、トップ営業や管理職の中には宅建を持っていない人も一定数存在します。逆に、宅建を持っていても契約が取れなければ評価されないという現実もあります。
そのため、「宅建を取ったのに評価されない」「なかなか内定が出ない」と感じる背景には、業界特有の“実力主義”が影響しているといえるでしょう。
宅建は仕事に直結しない?必要とされ続ける3つの理由

「宅建を取ったのに仕事がない」という声がある一方で、実際には宅建が今も必要とされている明確な理由があります。
ここでは、宅建士が社会において求められ続けている根拠を、3つの視点から紹介します。
宅建士は法律で配置が義務づけられている
不動産会社は、宅地建物取引業法により「従業員5人につき1人以上の宅建士を配置する」ことが義務づけられています。
この「専任の宅建士」の要件を満たさなければ、営業許可を維持できないため、業界として宅建士の需要は常に存在します。
たとえ資格保有者が増えても、企業が一定数の有資格者を確保しなければならない構造は変わりません。つまり、宅建士の存在は今も必要不可欠なのです。
宅建業務はAIには代替できない
宅建士の業務には、法律上AIが代行できないものがあります。契約書の作成や重要事項説明は、法的に人間が対応しなければならず、自動化が難しい業務です。
また、売主・買主との交渉や契約条件の調整は、状況に応じた柔軟な判断が求められるため、AIでは対応しきれません。
こうした業務には専門知識と実務経験が不可欠であり、今後も宅建士の役割は重要であり続けるでしょう。
不動産以外の仕事でも宅建は活かせる
宅建の知識は、不動産業界以外でも役立つ場面があります。
たとえば、銀行では不動産担保ローンの審査業務、建設会社では用地仕入れや開発事業の提案、法律事務所では不動産取引をめぐる調査や手続きなどです。
また、不動産投資や相続対策の相談に応じるFPや保険営業においても、不動産に関する知識が強みになることがあります。
業務の中心に宅建があるわけではなくても、「知識がある人材」として評価される可能性は十分あるのです。

住宅・不動産業界の
無料キャリア相談、
やってます。
現場のプロに
直接質問してみませんか?
\会員登録不要・簡単30秒!/
不動産業界で宅建があれば有利な職種とは?

宅建は不動産業界の中でも、職種によっては強力な武器になります。
「宅建を活かせる仕事って、結局どれなの?」と感じている方のために、ここでは特に宅建が有利に働く代表的な職種を紹介します。
営業(不動産売買・賃貸仲介)
不動産業界では、特に契約時の重要事項説明ができる宅建士が重宝されます。
特に売買仲介では、取引が高額で権利関係が複雑です。数千万円の取引では買主は慎重になり、専門知識を持つ担当者からの説明を求めます。
また、宅建資格があれば物件紹介から重要事項説明、契約締結まで一人で完結できるため、顧客との信頼関係を途切れさせずに取引を進められます。
宅建が必須の企業では資格手当が支給されることが一般的で、月額1万円〜3万円程度(年間で12万円〜36万円)の手当が付くケースが多く、収入アップにもつながります。
不動産管理(賃貸管理・マンション管理)
不動産管理の仕事では、オーナーに代わって物件の管理を行い、入居者対応や契約業務を担当します。
特に賃貸管理では、契約時の重要事項説明を行うために宅建士の資格が求められる場面が多くあります。
また、宅建士の専任要件があるため、不動産管理会社では一定数の宅建士を確保する必要があります。そのため、安定した需要があり、業界未経験でも宅建を持っていれば採用されやすい職種の一つです。
事務職(契約・ローン業務)
不動産業界の事務職でも、宅建資格があるとキャリアアップにつながります。
契約書の作成やローン関連の業務では、宅建の知識が役立つため業務の幅が広がるでしょう。
また、1~3月(新生活シーズン)や9月(転勤シーズン)の繁忙期などは不動産取引が活発化します。このため、重説を読める宅建士が不足しがちになり、資格を持っていると採用されやすい傾向があります。
上記のほか、用地仕入れや企画・商品開発部門などでも、宅建の知識が評価されることがあります。
契約・調査・法令に関する理解が必要なポジションでは、宅建を持っていることが一つの強みにもなるでしょう。
住宅・不動産業界の
無料キャリア相談、
やってます。
現場のプロに
直接質問してみませんか?
\会員登録不要・簡単30秒!/
宅建だけでは足りない?組み合わせると強い資格とスキル

宅建資格だけでは転職市場での競争力が十分とは言えませんが、他のスキルや資格と組み合わせることで価値を高めることができます。
- 営業職:ファイナンシャルプランナー(FP)
- 不動産管理:賃貸不動産経営管理士、マンション管理士、管理業務主任者
- 独立:不動産鑑定士、司法書士、行政書士
営業職を目指すなら
営業職では、宅建資格に加えて「ファイナンシャルプランナー(FP)」の資格があると、顧客への提案力が格段に広がります。住宅ローンや資金計画に関する相談が多いため、お金に強い営業担当として信頼を得やすくなります。
また、実際の営業現場では、コミュニケーション力やヒアリング力、物件を魅力的に伝えるプレゼンテーション力も重視されます。
地域情報に詳しいことや、顧客のニーズを正確に読み取る力も、成約率を左右する重要なスキルです。
不動産管理を目指すなら
不動産管理では、契約・更新・退去などの実務において専門性が問われます。宅建と相性がよいのは「賃貸不動産経営管理士」「マンション管理士」「管理業務主任者」などの管理系資格です。
近年ではこれらを合わせて「不動産資格四冠」と呼ばれることもあります。
加えて、クレーム対応やトラブル処理など現場力が求められるため、冷静な判断力やマルチタスク能力、そしてオーナー・入居者双方との円滑なコミュニケーションスキルが活かされます。
独立を視野に入れるなら
将来的に不動産業で独立・開業を目指す場合、宅建資格は必須条件の一つです。
さらに「不動産鑑定士」「司法書士」「行政書士」など、契約や権利関係に強い国家資格を組み合わせることで、より専門性の高いビジネス展開が可能になります。
また、収益物件の選定や収支シミュレーション、不動産投資に関する提案などを行うためには、資産運用や税務知識、経営感覚も求められます。
単なる「資格保有者」ではなく、「経営者」としての視点を磨くことが大切です。
不動産転職のために宅建を取るべき?取得におすすめの人

ここからは「宅建を取ったのに活かせていない」とならないためにも、どんな人に向いているのかを解説します。
- 不動産業界に挑戦したい人
- 不動産業界でキャリアアップを目指す人
- 将来的に独立や副業を考えている人
- 中高年・キャリアチェンジを考えている人
不動産業界に挑戦したい人
未経験から不動産業界に転職したい人にとって、宅建は客観的に知識を証明するツールのひとつになります。
特に、異業種からの転職では「業界知識がある」「学ぶ意欲が高い」と見なされ、未経験でもスタートしやすくなるでしょう。
なかでも不動産営業や賃貸管理、契約事務などの仕事では、資格があることで採用時の評価が上がりやすくなります。
不動産業界でキャリアアップを目指す人
すでに不動産業界で働いている人にとっても、宅建は昇進や年収アップにつながる重要な資格です。
特に、宅建士の資格手当が支給される企業では、年収が数十万円増えることもあります。また、契約業務を担当できることで、専門性が高まり管理職への道も開けるでしょう。
将来的に独立や副業を考えている人
宅建資格は、不動産業での独立開業や副業を考えている人にとって大きな武器になります。
不動産業を営むには宅建業の免許が必要で、専任の宅建士を置くことが義務付けられています。自分で資格を持っていれば、宅建士を雇う必要がなく、開業コストを抑えられるというメリットがあります。
また、不動産仲介やコンサルティング業務を個人で行う場合も、資格があることで信頼性が増し、仕事を獲得しやすくなります。
「宅建士がいないとそもそも開業できない」ため、独立を視野に入れているなら取得しておくべき資格といえます。
中高年・キャリアチェンジを考えている人
宅建は「40代・50代」「女性」など、年齢や性別に関わらず活かせる資格です。
特に不動産業界では、顧客との信頼関係が重要視されるため、生活経験が豊富な中高年層や女性が強みを発揮できる場面も多くあります。
「50歳からでも遅くない」という視点で、セカンドキャリアとして宅建資格を活用する道も考えられます。
宅建は仕事につながる資格!大切なのは活かし方

宅建資格はさまざまな仕事で活かせる可能性を持っていますが、「資格があるから必ず転職に成功する」とは限りません。
自身の経験や志向に合った働き方を見つけ、スキルや他資格と組み合わせていくことで、取って終わりではなくキャリアを支える武器になります。
「宅建を活かしたいけれど、どう進めたらいいかわからない」という方は、住宅・不動産業界特化の転職エージェント「住まキャリ」にぜひご相談ください。
あなたにマッチする住宅・不動産の求人をご紹介
30秒で登録完了!
住宅・不動産業界の経験はございますか?